観光による地域の再生を考える~観光地域づくりの実践から~
日時:2025年6月7日(土)10:00〜11:30
場所:6番教室

観光学高等研究センター 准教授
小泉大輔先生
「住んでよし、訪れてよしの国づくり」の理念の下、国策としての観光が強力に推し進められて20年余り。訪日旅行客数(インバウンド)は目標値を上回る飛躍的な伸びを示してきた一方でオーバーツーリズム等の新たな社会問題をもたらしている。地域再生への処方箋として「観光」はいかに貢献できるのか。観光地域づくりの現場に携わってきた経験を踏まえ、改めて考えてみたい。
アイヌ文化の復興ー人間性の再生
日時:2025年6月7日(土)17:00〜18:30
場所:6番教室
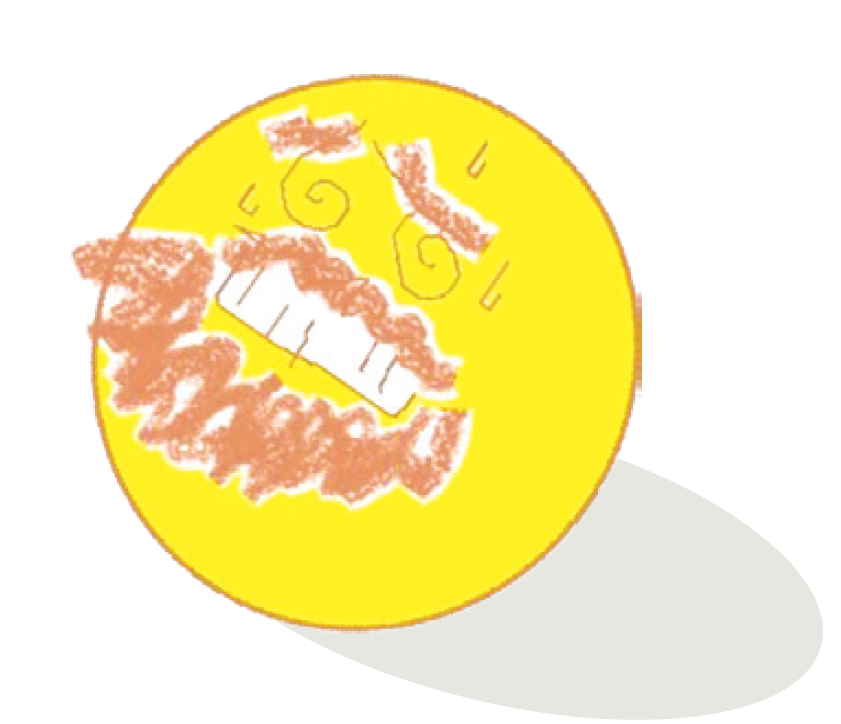
アイヌ・先住民研究センター 准教授
北原モコットゥナシ先生
民族共生象徴空間ウポポイでは、多くのアイヌ民族が働きながら、自らの文化を学び、発信に取り組んでいます。また、本学でも、アイヌ出自の構成員(教職員、学生など)が、自らの文化の回復や維持と研究や教育といった大学の諸活動を両立することが可能となるように、様々な取り組みが進められています。 アイヌ民族は近代に入るまで国家に帰属せずに生活してきましたが、北海道や樺太など、それまでの居住地が日本やロシアによって植民地とされる中で、基本的な権利や自由な選択を制限され、言語や文化の維持も困難になりました。これは、アイヌ民族の人間性が否定されるとともに、他者の犠牲の上に「豊かさ」や拡大拡張を求めた点で、入植者の側も人間性を喪失していく過程であったと言えます。先住民族文化の復興とは、単なる文化の取り戻しを越え、私たちの社会全体が人間性を回復させていくことでもあるのです。
子供の問題に発達をみる
日時:2025年6月8日(日)10:00〜11:30
場所:6番教室

大学院教育学研究院 教授
加藤弘通先生
私はいじめや非行、ひきこもりといった世間では「問題」とみられる現象を発達という視点から研究しています。 一般的に問題が起きるのは、発達がうまくいっていないからだと考えられることが多いです。しかし、発達心理学の視点からすると、発達しているからこそ問題が起きていることも多々あります。 この講義では、子どもの問題を単に発達の「失敗」ととらえるのではなく、「発達しているからこそ問題が起きているのではないか?」という視点から子どもの問題を考え、子どもの問題を「活かす」視点を、聞きに来てくださったみなさんと共有できたらと思います。
国際刑事裁判所(ICC)の「再生」?
日時:2025年6月8日(日)13:30〜15:00
場所:6番教室

大学院法学研究科 准教授
横濱和弥先生
ロシア・ウクライナ戦争、ガザ紛争、そしてアメリカとの関係性――。 国際法上の重大犯罪を訴追・処罰を任務とするICCは、混沌とする世界情勢の中で、何を果たすことができ、あるいはできないのか。 最近の情勢を踏まえて、なるべく分かりやすく解説します。